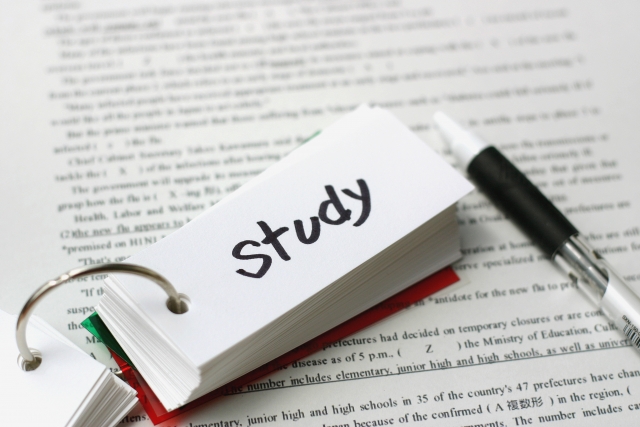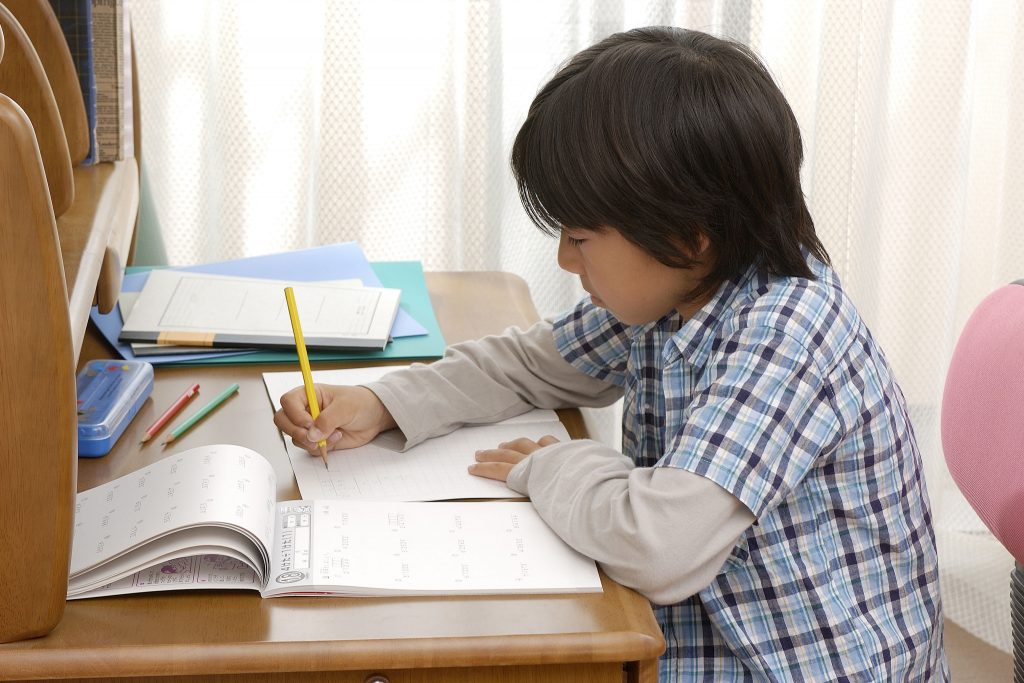なぜ6月は“水無月(みなづき)”なのに雨ばっかり?名前のナゾを解説!
「水が無い月」なのに、梅雨まっさかり…?
こんにちは、家庭教師のアズです!
6月に入って、雨の日が続く季節になりましたね。ところでみなさん、「6月=水無月(みなづき)」という名前、聞いたことありますか?
“水が無い”と書くのに、実際は雨が降りまくるこの時期…。なんだか不思議ですよね。
今日は、そんな「水無月」という名前のナゾを、雑学風にスッキリ解説していきます!
“無”は「ない」じゃなくて「の」だった!?
「水無月」は“水が無い月”と読むと、一見「水不足の月?」と思ってしまいますが、実はそうではありません。
ここでの「無」は、“の”という意味の古語。
つまり、「水無月」は“水の月”という意味になるんです!
これは、田植えのために水が必要になる月=“水の月”という解釈が由来とされている説が有力。
ちょうど6月は、昔の農業カレンダーでも水を張った田んぼが目立つ季節でした。
他にもある!“無”が“の”になる言葉
実はこのように、「無」が“の”として使われるケースは他にもあります。
たとえば、
- 風無く(かぜなぐ)=風のないこと
- 夜無く(よなぐ)=夜のこと
など、和歌や古文の中ではしばしば登場します。ちょっとした古文のトリビアにもなりますね。
じゃあ、なぜ誤解されやすいの?
今の日本語では「無=ない」と読むのが一般的なので、「水無月」と見るとつい“水が無い月”だと思ってしまいます。
しかし、名前のルーツをたどると、むしろ「水が豊かな月」だったという、ちょっと逆説的な面白さがあるんです!
まとめ:言葉の由来を知ると、世界が広がる!
6月=水無月。その名前には、「昔の日本人が自然と向き合っていた暮らしの知恵」が詰まっています。 普段何気なく使っている言葉にも、こんな奥深い歴史や意味があるんですね。
勉強に疲れたときは、こうした言葉の豆知識でリフレッシュするのもおすすめです!
それでは、じめじめの6月も、元気に乗り切っていきましょう!